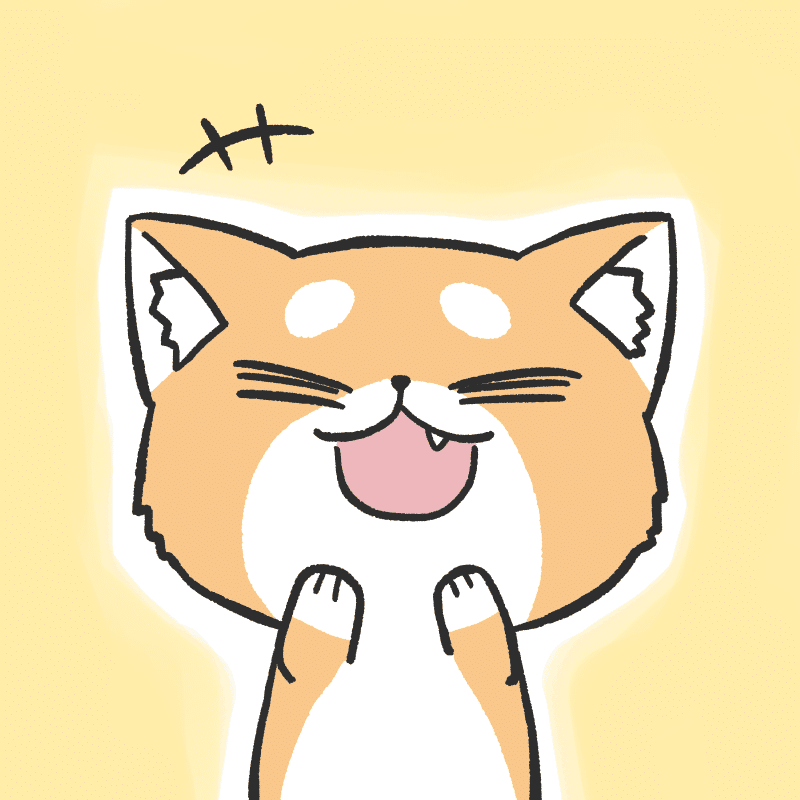- Shopify
- 2025.02.16
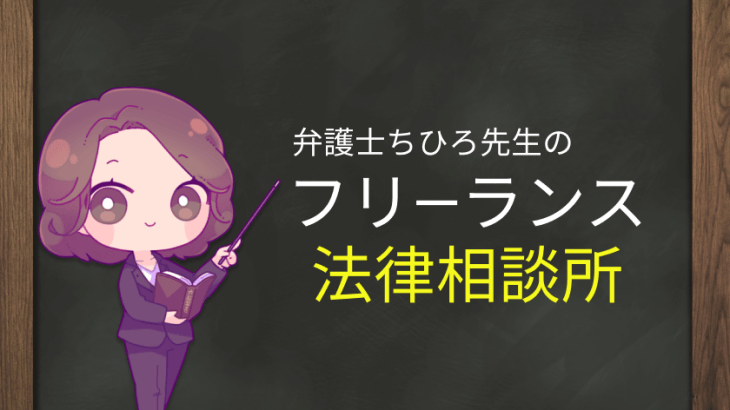

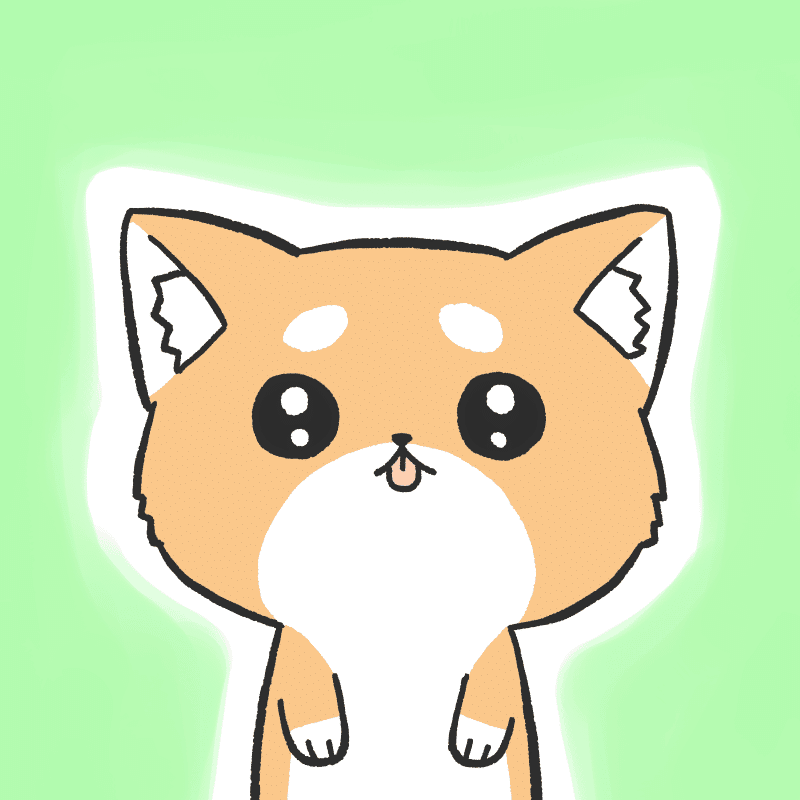

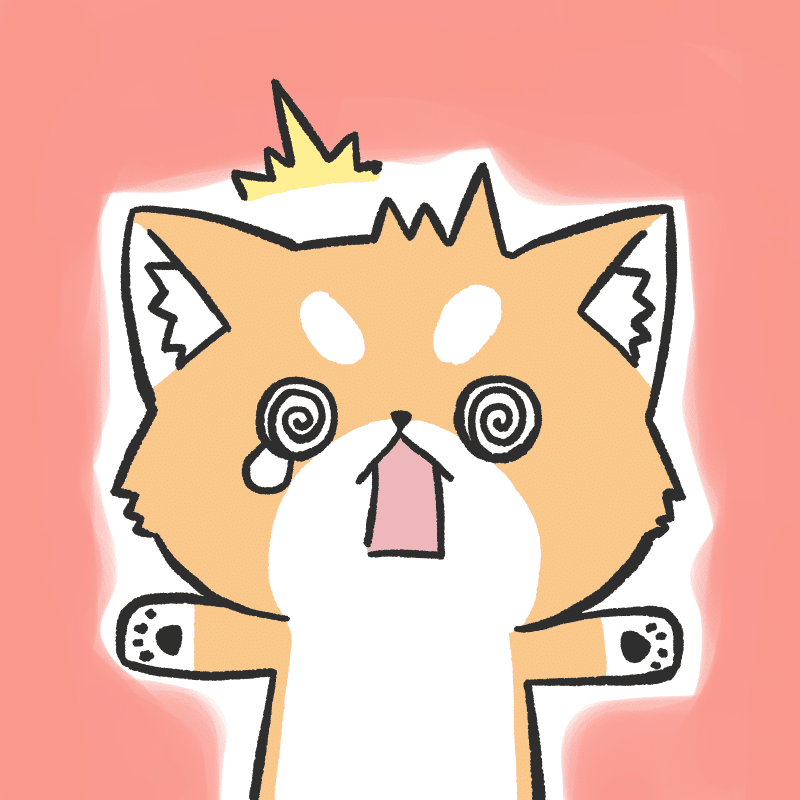

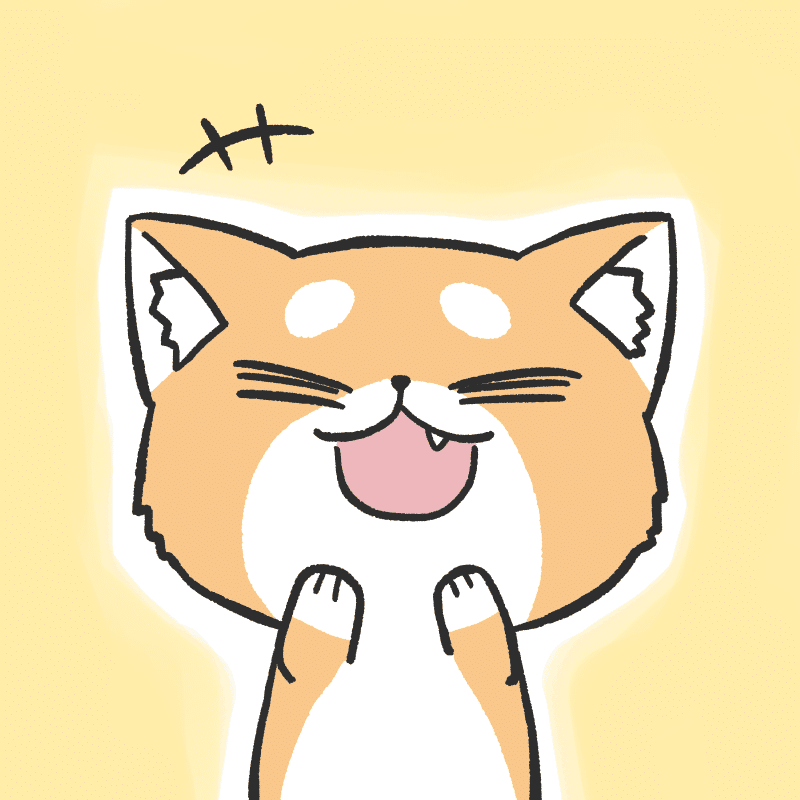

連載第2回で述べたように、「業務委託契約」という時には、成果物の納品が求められる請負契約と、求められない準委任契約があります。これらは1枚の契約書の中で混合している(「ここから請負、ここから準委任」)ときもあるので、注意が必要です。
契約で大切なのは、契約書のタイトルではなく、実質どんな契約であるかです。「業務委託契約書」と書いてあっても、その内容が、常駐先の指揮命令に従うものであったら、それが実質的に雇用契約になっています。自分が望まない働き方をしないように、内容をしっかり確認しましょう。
フリーランスと発注者の関係は、「雇用」ではないので、労働基準法の適用はありません。でも、契約内容によっては、圧倒的にフリーランスに不利な内容を結んでしまい、労働基準法が定める条件以下のセルフブラック状態になる可能性もあるので、気をつけましょう。
雇用契約ではないフリーランスですが、近年の働き方改革の波に乗って数が増えつつあり、厚生労働省の有識者会議「雇用類似の働き方に係る論点整理に関する検討会」(鎌田耕一座長)は2019年4月23日に、第10回会合を開きました。この会議では、フリーランスを「雇用類似」の関係と位置付けて、報酬の支払い確保や報酬額の適正化などの課題について議論し、今夏をメドに報告をまとめる予定です。この報告が、今後法律化すれば、フリーランスの報酬額にも、なんらかの最低限度額が定められる可能性があります。
下請法は、正式名称は『下請代金支払遅延等防止法』といい、その名の通り、立場の弱い、下請けに対する支払いが過度に遅れることを防止するために作られました。法人ではないフリーランスも、コンテンツ作成などの業務を行う場合、資本金額1000万円超の事業者との取引に関して、下請法上の『下請事業者』となります。下請事業者であるフリーランスに対しては、①書面による契約の締結、②成果物の受領拒否の禁止、③60日以内の支払い義務など、不利益な行為が禁止されますので、覚えておきましょう。
「下請法に該当するのかな?」と疑問に思う場合には、公正取引委員会のガイドラインをぜひ一度読んでみてください。法律そのものよりも具体的な内容がわかります!
また、「困ったけど、誰に相談したらよいかわからない」という時には、全国に「下請かけこみ寺」(https://www.zenkyo.or.jp/kakekomi/ )があり、無料で相談できます。
独禁法には、建設業などの大企業が談合することを禁止するというようなイメージがあります。しかし、実は、フリーランスが今後も増加することが見込まれるので、同法の目的である、公正かつ自由な競争を促進するためには、フリーランスが適正な取引条件と報酬を受ける権利を保護する必要があるとして、公正取引委員会で議論され、2018年2月15日に報告書が出されています(https://www.jftc.go.jp/cprc/conference/index_files/180215jinzai01.pdf )。この報告書の内容が、今後の独禁法の運用に影響を与えるとされています。
報告書で指摘されているのは、フリーランスからみた発注者企業が、その優越的な地位に基づいて行う行為のうち、行き過ぎのものを規制しよう、というものです。例えば、実質的に他の取引先と契約ができなくなるような「専属契約」的な条件や、成果物を他で使えないようにする利用制限、競業避止義務などが、多くみられるものです。業務委託契約の締結に当たっても、これらの条件については、独禁法の観点から規制される可能性があります。今後は注意するべきポイントです。
東フリ読者の皆さんの多くは、エンジニアやライターのお仕事をされていると思います。そのような方々が成果物について気をつけるべきなのは、著作権の処理をどうするかです。多くのお仕事では、納品後や報酬支払いのタイミングで、著作権を発注者に譲渡する条件が多くみられます。しかし、そもそもフリーランス自身のものでない権利や、他の案件でも使うような共通の部分についても権利譲渡をしないようにするなど、チェックすべきポイントがありますので、気をつけましょう。
なんとなく、「紙にしてハンコを押さないと契約は有効にならない」と思いがちですが、実は、「口約束」で契約自体は成立します。ただし、何をいつ合意したのかが不明確になるので、リスクヘッジのために、契約書は作りましょう!
紙で印刷する以外にも、近年は電子署名の方法で契約書の捺印ができるようになりました。代表的なサービスは、cloudsign(https://www.cloudsign.jp/)などです。
電子署名サービスを使って契約すると、紙の契約書の際に必要となる収入印紙が不要になりますし、郵送などの手間も省けますので、とってもオススメです!
民法は、契約のことだけでなく、結婚や離婚といった家族関係も含めた、とても広い範囲を決めている法律です。その中には、絶対守らなければならない「強行規定」と、当事者の合意で別な内容を決められる「任意規定」があります。
請負契約によくある「瑕疵担保」も実は任意規定。当事者の合意で、排除できます。取引関係は、基本的に当事者の自由にしようという考えから、契約関係についての規定はほとんどが任意規定です。もちろん、やりすぎは、無効になります。